【2025年】車検の法定費用はいくら?車種別・重量別の費用を解説

車検にかかるお金の中で、かならず支払わなければならないのが「法定費用」ですが、その費用は車種や重量によって異なります。
ときどき勘違いされますが、法定費用は依頼先(ディーラーや工場など)によって変わることはありません。
依頼先によって車検代が異なるのは、法定費用以外の金額が影響しているためです。
今回はこうした車検の基本的な内訳から、法定費用の車種別・重量別の目安金額、車検費用を抑える工夫について解説していきます。
【費用を抑えたい方へ!熊本で割引が豊富な車検店舗を探す】
車検費用を賢く抑える鍵は依頼先によって変わる「整備費用」にあります。
法定費用は避けられませんが、トータルコストを下げることは可能です。
熊本県を拠点とする九州産交オートサービスなら、早期予約やネット予約の割引で整備費用を大幅に抑えられます。
まずはあなたがお得に車検を受けられる、お近くの店舗を見つけてみましょう!
目次
車検代に含まれる法定費用に依頼先ごとの違いはない!

自賠責保険料・自動車重量税・印紙代の3つをまとめて「法定費用」と呼びますが、この法定費用がディーラーや工場などの依頼先によって変わることはありません。
なぜなら法定費用は国が金額を提示しており、ディーラーや工場などが勝手に金額を変更することはできないためです。
提示される車検費用は、法定費用と「車検基本料」や部品代などを合わせた金額です。
このうち法定費用以外の部分はディーラーや工場側で設定ができるため、依頼先によって車検費用が異なるわけですね。
自賠責保険とは
自賠責保険は、交通事故で相手を死傷させた場合の被害者救済を目的とした保険です。
その補償範囲は対人事故に限られており、対物や自分の車の修理代は対象外となります。
自賠責保険は、正式には「自動車損害賠償責任保険」と呼ばれ、車で公道を走るうえで必須となる保険であるため「強制保険」と呼ぶことも。
ちなみに、自賠責保険では対処できない損害を補うために存在するのが「任意保険(自動車保険)」です。
任意保険は強制ではありませんが、多くのドライバーが加入しています。
関連コラム:車検と自賠責の期限がずれるのは普通?損しないための基礎知識
自動車重量税とは

自動車重量税は、その名の通り車の重さによって税額が決まる国税です。
ただ、重さ以外にも税額を決定する基準があります。
- 車種(軽自動車か普通車か)
- エコカー減税の対象車かどうか
- 新規登録からの経過年数
環境性能に優れた車ほど優遇される一方、古い車は税額が高くなる傾向があります。
印紙代(検査手数料)とは
印紙代は、車検に必要な検査を受けるための手数料です。
「検査手数料」と言った方が分かりやすいかもしれませんね。
印紙代は国土交通省や軽自動車検査協会へ支払う形になっており、車の種類によって金額が決まっています。
普段あまり意識することのない項目ですが、車検を受ける際にはかならず発生します。
参考資料:国土交通省「登録・検査手数料一覧表」
車種・重量別の法定費用の違いについて

法定費用が依頼先で変わることはありませんが、車種や排気量ごとに金額の差があります。
まず軽自動車と普通自動車では自賠責保険料や重量税が異なり、同じ普通車であっても重量が増えるほど高くなるのが一般的です。
詳細は下記項目ごとに表でまとめました。(※)
- 軽自動車の場合
- 自家用普通乗用車(0~1t)の場合
- 自家用普通乗用車(1~1.5t)の場合
- 自家用普通乗用車(1.5~2t)の場合
- 自家用普通乗用車(2~2.5t)の場合
- 自家用普通乗用車(2.5~3t)の場合
- 輸入車の場合
※自賠責保険の加入期間は、25カ月分を想定。
※印紙代(検査手数料)は指定工場(OSS申請除く)への依頼を想定。
※エコカー減税対象車などはこの限りではありません。
※自動車重量税は、車両重量が0.5t以下のものから設定されていますが、現在の日本では0.5t以下の乗用車はほとんど販売されていないため、今回は除外。
軽自動車の場合
| 自動車重量税 | 自賠責保険料 | 印紙代 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 6,600円 | 18,040円 | 1,800円 | 26,440円 |
軽自動車の法定費用は約26,000円です。
軽自動車の自動車重量税も、普通乗用車と同様に登録年数による変化があります。
車の登録から13年が経過した場合、自動車重量税は8,200円に。
18年が経過した場合は8,800円に値上がりします。
関連コラム:軽自動車の車検費用はいくら?相場と節約方法を解説
自家用普通乗用車(0~1t)の場合
| 自動車重量税 | 自賠責保険料 | 印紙代 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 16,400円 | 18,160円 | 1,800円 | 36,360円 |
車両重量が0〜1tの普通乗用車の場合、法定費用は約36,000円です。
軽自動車よりも1万円近く金額が異なりますね。
該当する自動車は
- トヨタ ヤリス
- スズキ クロスビー
などです。
車の登録から13年が経過した場合、自動車重量税は22,800円に。
18年が経過した場合は25,200円に値上がりします。
関連コラム:普通車の車検費用はいくら?内訳と相場・業者別の違いを徹底解説
自家用普通乗用車(1~1.5t)の場合
| 自動車重量税 | 自賠責保険料 | 印紙代 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 24,600円 | 18,160円 | 1,800円 | 44,560円 |
車両重量が1〜1.5tの普通乗用車の場合、法定費用は約44,000円です。
これくらいの重量からセダンなどの車両が増えてきます。
比較的軽量なミニバンも含まれるようになります。
該当する自動車は
- トヨタ シエンタ
- ホンダ ヴェゼル
- 日産 オーラ
などです。
車の登録から13年が経過した場合、自動車重量税は34,200円に。
18年が経過した場合は37,800円に値上がりします。
自家用普通乗用車(1.5~2t)の場合
| 自動車重量税 | 自賠責保険料 | 印紙代 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 32,800円 | 18,160円 | 1,800円 | 52,760円 |
車両重量が1.5~2tの普通乗用車の場合、法定費用は約52,000円です。
単純に車体が大きくなると重量も増すため、ワゴンやミニバン、SUVが多い傾向にあります。
該当する自動車は
- スバル フォレスター
- トヨタ ハリアー
- マツダ CX-5
などです。
車の登録から13年が経過した場合、自動車重量税は45,600円に。
18年が経過した場合は50,400円に値上がりします。
自家用普通乗用車(2~2.5t)の場合
| 自動車重量税 | 自賠責保険料 | 印紙代 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 41,000円 | 18,160円 | 1,800円 | 60,960円 |
車両重量が2〜2.5tの普通乗用車の場合、法定費用は約60,000円です。
これくらいになると、一目で重量感が伝わるような車ばかりになりますね。
該当する自動車は
- トヨタ アルファード
- レクサス NX
などです。
車の登録から13年が経過した場合、自動車重量税は57,000円に。
18年が経過した場合は63,000円に値上がりします。
自家用普通乗用車(2.5~3t)の場合
| 自動車重量税 | 自賠責保険料 | 印紙代 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 49,200円 | 18,160円 | 1,800円 | 69,160円 |
車両重量が2.5~3tの普通乗用車の場合、法定費用は約69,000円です。
これほどの重量になると、メルセデス・ベンツやアウディなど輸入車メーカーによる車や、センチュリーのようなショーファーカー(※)が該当するように。
該当する自動車は
- トヨタ ランドクルーザー
- レクサス LX
- トヨタ センチュリー
などです。
車の登録から13年が経過した場合、自動車重量税だけで68,400円に!
18年が経過した場合は75,600円に値上がりします。
※専従の運転手がおり、搭乗者は後席でリラックスするタイプの車。
輸入車の場合
輸入車(外車)だからといって、法定費用が特別変化するわけではありません。
国産車も輸入車も、法定費用は同じ条件で提示されます。
ちなみに、一般的に「輸入車の車検費用は高い」と言われてしまうのは
- 輸入車は国産車よりも重いものが多く、その分重量税に加算されがち
- 輸入車は部品代や車検基本料が高くなりがち
などが原因です。
部品も外国からの取り寄せだったり、車検や点検に専門の機器が必要だったりと、コストがかかってしまうわけですね。
法定費用以外の不安を解消!熊本で整備費用をクリアに
費用を抑えるポイントは、依頼先で差が出る「整備費用」を適正化することです。
熊本県内で安心できる整備内容と、納得のいく費用を両立させるなら、九州産交オートサービスにご相談ください。
過剰な整備を提案せず、あなたの疑問に誠実にお答えします!
まずはお気軽に無料相談をご利用ください。
法定費用に関するよくある疑問
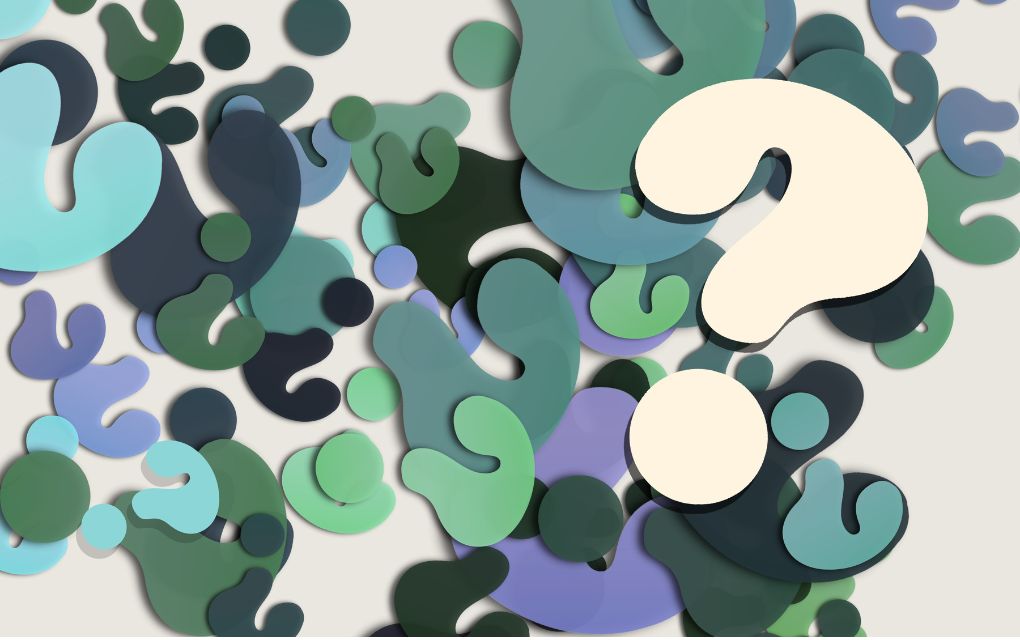
法定費用の支払い方法や支払いのタイミングなど、抱きがちな疑問について回答します。
- 法定費用はいつ支払う?
- クレジットカード払いはできる?
- 納税証明書を紛失した!どうすればいい?
Q.法定費用はいつ支払う?
法定費用の支払いは車検前、入庫するタイミングで支払うことが多いです。
車検の依頼先によって異なるため一概には言えませんが、前払いの方が多い傾向にありますね。
前払い以外の場合だと車検後、車を引き取るタイミングで支払います。
関連コラム:車検は何年ごとにしないといけない?普通車・軽自動車の周期と確認方法を詳しく解説
Q.法定費用のクレジットカード払いはできる?

法定費用のクレジットカード払いは難しいでしょう。
多くの場合、法定費用の支払いは現金が基本です。
法定費用は業者を通して国や保険会社に支払われるものであるため、カード払いをした場合に発生する手数料は業者側が負担しなくてはなりません。
法定費用は業者の利益にはならない費用であるため、法定費用のカード払いは業者側のマイナスになってしまうわけですね。
ただ、依頼先によってはカード決済に対応している場合もあります。
しかし車検基本料などはカード払いが可能でも法定費用だけは現金のみ、という業者もあるため、事前に確認しておくと安心でしょう。
Q.納税証明書を紛失した!どうすればいい?
一部地域では再発行しなければなりませんが、多くの地域では納税証明書を紛失しても再発行などは不要です。
以前は車検時に納税証明書の提示が必要でしたが、電子化が普及した現在では書類がなくてもシステム上で納税状況の確認ができるようになっています。
ただし、すべての地域で納税証明書の電子化が進んでいるわけではないため、一部地域では今まで通り書類の提示が必要です。
書類が必要な場合は、各都道府県の自動車税事務所および、その支所、または各県税事務所(普通乗用車の場合)にて、または自身の居住区を管轄している市役所(軽自動車の場合)で手続きを行いましょう。
郵送での手続きも可能です。
【法定費用以外は賢く節約!熊本で割引豊富な店舗を探す】
法定費用以外の「整備費用」であれば、お得な割引を活用し、総額を大きく抑えることが可能です。
熊本県内でネット予約割引や早期割引といった豊富な特典を用意している九州産交オートサービスなら、あなたの賢い車検準備を費用面で強力にサポートします。
お得に車検を済ませるお近くの店舗を、今すぐ見つけてみましょう!
車検費用を抑えるためには法定費用以外の見直しがポイント

車検費用を抑えたいときは「基本料金」や「整備代」などの、依頼先ごとに変化する部分の見直しが重要です。
車検費用をできるだけ抑えるためには日頃から、または依頼先を選ぶ際に下記のポイントを意識してみましょう。
- 複数業者から見積もりをとって比較する
- 定期的な点検で早期トラブルを防ぐ
- 普段からのメンテナンスで故障リスクを下げる
- 整備項目を事前に確認する
複数業者から見積もりをとって比較する
車検の費用は業者によって差があるため、1社だけで決めるのは少しもったいないかもしれません。
特に、ディーラーと民間整備工場では料金や整備内容に違いがあることも十分ありえます。
複数の見積もりを比較することで、納得のいく価格とサービスを選べるようになるでしょう。
相場を知るうえでも、見積もりの比較は有効です!
定期的な点検で早期トラブルを防ぐ
定期点検は費用がかかるものの、車検時の大きな出費を防ぐある種の「保険」のような役割も果たします。
例えば、オイル漏れや部品の摩耗などを早期に発見できれば、車検時の修理が不要になることもあります。
1年ごとの点検を欠かさず行うことで、トラブルの芽を早めに摘むことが可能です。
早期発見していれば軽度の修理で済んでいたものが、数年放置していたために大きな修理に発展してしまった……ということも実際に起こりえます。
定期的な点検・メンテナンスは、こうしたリスクを回避するための重要な工程なのです。
普段からのメンテナンスで故障リスクを下げる

「異音がするけど、まぁ大丈夫だろう」
そんな油断が大きな修理につながることもあるのです。
日常のメンテナンスを怠らないことで、突発的な故障を防ぎやすくなります。
エンジンオイルの交換やタイヤの空気圧チェックなど、基本的な点検を習慣化しておくと安心ですね。
費用を抑える第一歩は、こうした「こまめな気配り」かもしれません。
整備項目を事前に確認する
車検時に必要な整備内容を事前に確認することで、無駄な出費を防ぐことにつながることがあります。
業者が「整備をした方が良い」と勧めるものの中には、車検の合格に関係のない「予備整備」が含まれることもあります。
もちろん予備整備は「ここで整備しておいた方が、将来的な故障リスクが少ない」などの理由があっての提案ですが、車検の合格には関係ありません。
「車検に合格する」ことを優先に、かつできるだけ費用を抑えたいのであれば予備整備を外してもらうことも検討してみましょう。
関連コラム:初めてでも安心!車検の受け方と流れを徹底解説【初心者向け基本のガイド】
法定費用は避けられない支出。抑えるなら整備費用の工夫を!

自賠責保険・重量税・印紙代の3つで構成される法定費用は、依頼先によって変わることはなく、車種や重量によってのみ金額が異なります。
そのため、節約したいときは、法定費用以外の部分を見直すのがポイント。
整備内容の工夫や定期的なメンテナンスなどで、支出を抑えることは十分可能です。
事前に情報を整理し、納得できる形で車検を受けられるよう準備していきましょう。

